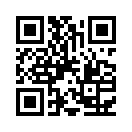2012年05月19日
旅にしあれば チベット編 その1
2012年5月19日(土)
好評の,かどうかわからないけど,昔書いた旅行記を引き続き掲載します。
今度は,「旅にしあれば チベット編」。1991年夏のこと。
はじめに
また旅に出ることになった。行き先はチベット。夏休みを利用しての2週間である。今回も旅行中のメモをもとに旅日記を綴ることにする。
今回の参加者は23名。うち女性は9名、年齢は23才から72才まで、京阪神を中心に九州、関東からも参加。ツアー団長は中国のチベット併合時にインドへ亡命し、その数年後来日されたチベット人のT先生。以来30数年間一度もチベットを訪れることかなわなかったが、このたびようやく初めてのお里帰りができることになったのだ。前回の、インド・ネパール・ブータンの旅でご一緒したメンバーのうち,私を含めて5名が参加した。
チベットは平均標高4000メートルの高地であり、まずは高山病の心配があった。思えば13年前富士山に登った折九合目あたりからひどい頭痛に悩まされ3歩進んでは休む胸突き八丁、あれが私の最初の高山病の経験であった。以来高地に弱いという思い込み深く、前回の旅行の際,標高1700メートルのカトマンズ空港での頭痛を高山病だと言い触らして笑われた。
今回は内科医K先生の伝手であらかじめ名古屋大学医学部の低圧室に入室する機会を得た。旅行に出る5日前のことである。8畳ほどの部屋の中で標高5000メートルの状態まで気圧を下げるというのである。このとき5名が一緒に入室したのだが、その中でまっさきに嘔吐したのは私であった。4500メートルを越えた途端のことだった。この後激しい睡魔とむかつき、頭痛は、3000メートル台に降りるまで続いた。以来“魔の4500メートル”が記憶されることになる。
不安はあったが、何とかなるだろうと思う。ただ、低圧室5000メートル地点での頭重感がもし何日も続くとすればいやだなと思った。高山病の予防としては漢方薬の柴苓湯あるいはダイヤモックスといういずれも利尿剤が効くという話であった。要は体の中に浮腫ができるので、それを外に追い出してしまうのがよいということらしい。チベットに着いたらなるべくたくさん水分を摂りなさいよ、とチベット旅行経験者に言われ、薬とお湯を頼りに出掛けることにする。
1991年7月26日 金曜日
7時45分の空港バスに乗り、空港8時40分着。国内線ロビーと国際線ロビーを間違え時間をロスし、集合時間を大幅に越えてコンダクター氏に迷惑をかける。今回はどうも準備段階からバタバタしてしまった。旅行前の多忙は厳禁と言われていたのに、出発前に仕事をためてしまい睡眠不足のまま旅行になだれこむことになったのだ。10時15分発のキャセイ航空でまずは香港へ。旅の入り口としての香港はあまりに日本に似ていて、個人的な感覚ではまだ旅の助走段階である。ハイ・テンション、早口の日本語を操る現地ガイドの許(きょ)さんにより浅水ビーチを案内されてこの日は暮れる。
1991年7月27日 土曜日
朝6時モーニングコール。眠りの中にドリルをさしこまれる。ここロイヤル・パシフィック・ホテルの朝食はお粥、パン、ワッフルなどが並ぶバイキング形式でなかなかおいしい。ゆっくり食べたかったが、廣州行きの列車は九龍駅8:18発のため、許さんにせきたてられ、駅へ。
湿度たっぷりの風景を見ながら約5時間列車に揺られる。この列車の中では蓋つきコップとジャスミン茶が配られ、女性乗務員が魔法瓶のお湯を配って歩く。愛想は悪い。
中国時間12時40分、廣州着。ここで、2人の現地ガイドに迎えられる。ひとりは胡さんという、成都出身の長身痩躯の青年。このひとが旅行のほとんどを同行してくれることになる“全線随行”のガイドなのである。いまひとりは張さんという小太りの中年男性で、廣州のみのガイドである。どういう仕組みか最後までよくわからなかったけれど、中国国内のガイドはすべて公立の旅行案内組織から送られ、どうやら、全線随行ガイドの他に各地で短期間のガイドもつけなければならないようだ。
張さんの“正しい”日本語の説明は許さんのそれに比べると耳に緩やか。繁華街の中山道、光孝寺、六榕寺、孫文記念館をみてまわる、が、暑い。湿気が多い。夕刻空港へ。ここで張さんと別れる。
飛行機で成都へ飛ぶ。移動が多くて疲れる。
錦江賓館での夕食時、コンダクター氏より良くないニュースが伝えられる。悪天候のため本日のラサ行きの飛行機は欠航。明日の便がもし飛べば、今日のあぶれたお客も乗り込むわけで、予約はとってあるものの、必ず乗れるという保証はないという。早めに空港に行く必要があるとのことで5時起床、5時30分出発となる。チベット入りに必要な十分な休息とは随分矛盾するハードスケジュールである。一筋縄ではいかない旅だという予感がこのころから芽生える。搭乗券を握り締めて大勢の客が我先にと飛行機目指して走るのだろうかなどとぼんやり思いつつ、部屋でなかなか届かない荷物を待つ。
1991年7月28日 日曜日
5時30分出発。まだ暗い中をバスは走る。畑の中の一本道を猛スピードで走る。そのバスの右手を大きな荷物を乗せた自転車が、同じくらい悠々と走っている。成都ではとにかくみんながひた走っている。
早朝のためまだ電気もつかない空港でアナウンンスを待つ。搭乗券はあっても乗れるという確証はない。あまり早く出て来たので、朝食もホテル提供のランチボックス。闇中摸索の味がする。
7時過ぎやっと空が明るくなって空港の外、もやの中に木立が見え出す。雰囲気がいい。ブッシュにも広葉樹にも、どちらにも偏らない緑。しっくいを壁に塗った平屋が点々と続く。
幸い、7時40分と7時50分、2便が飛ぶことになり、ラサまで行けることがわかる。7時50分離陸。
ラサに着いたら猛烈に空気はきれいし、調子に乗ってフワーッとなってしまう。4時間は皮膚呼吸で保っていられるが、その後がくっとくる。支えられてフラフラになって歩いとったフランス人を見たが、あれはかっこわるいなあ
出発前Dr.Kに聞いた話である。着いてすぐは妊娠後期の女性のごとくそろりそろりと歩かねばならないという示唆もあった。しかし飛行機の中にいる限り、まだ想像つかない。
10時ラサ空港着。標高3500メートル。空気が冷たい。空が澄んでいる。空港の周りに雪を戴いた山。空港は、一度も建物の中を通過することなく、門すらもない。チベットが飾らなくてやさしく思えるのに、この空気の中に、この気候の中に、私の体力を奪っていくものが隠れているのだろうか。半信半疑。
バスの準備が整うまで、気功のまねごとなどして待つ。手の平を上に向けて陽の動きにすると、空気が暖かく、逆に手の平を下向けにした陰の形では冷たく感じられる、ような気がする。なんとなく頭がぼーっとして幸福な感じなのは高山病のきざしか。寝転ぶと大地のひんやりした感触が伝わってくる。フロントグラスのひびをテープで補強したバスに乗り込む。チベット人ガイドのロマさんという若い女性が加わる。
チベット第1日の今日はなるべく低い土地で、という配慮から、直接ラサ入城せず、南のツェダンへ。
途中ヨンブ・ラカンを見る。ここはチベットの父祖降臨の地。小高い丘の上に古い寺がある。バスから降りると子どもらが駆けてくる。“こんにちは”は“タシデレ”。ラヒという名の男の子と一緒に寺へ登る。歩きながらチベット単語を教えてもらう。目はミ、鼻はナゴ、口はカー、あごはオマ、耳はアンジュ、頭はゴーで、脚はガンバ。寺の上には塔があり、何十年もの間お経を書き写している老人がいた。塔の上の小窓から東の方向にタルチョンがいくつもしがみつくような感じで揺れている。チベットは犬が多い。あちこちでのっそり寝そべっている。寺の階段もベッドにしていて笑ってしまった。子どもたちと別れ、バスに乗る。
昌珠寺へ。ここには真珠でできた観音像があった。人を助け疲れてしばし休息しているという。左肩にかしいだポーズが優雅。ここにも子どもが群れていて、先程の寺の子よりもactiveに、手をつなぐのを求めてくる。年長の少年がこっち、と指で合図しては“マショー”とか“ヤンソー”とか言う。“行こう”という意味かと思って、私も「マショ、マショ」と言いつつついていく。2才前くらいの男の子も子ども集団に一人前にまじっていて、関西でいうところの“ゴマメ”か。ひとりで行動できるときはひとりで、はしご状の階段では、年長の女の子が手を貸したり、おんぶしたりする。必要なときに面倒をみてやるのが極めて自然である。
ツェダン・ホテル着。食後胃にむかつきを覚え、ダイヤモックス2錠、柴苓湯、セデス服用、大量の水を飲む。20分ほどして痛み和らぐ。明日は、王家の墓を見る予定を変更して、チベット最古の寺,サミエ寺を訪れることになる。
好評の,かどうかわからないけど,昔書いた旅行記を引き続き掲載します。
今度は,「旅にしあれば チベット編」。1991年夏のこと。
はじめに
また旅に出ることになった。行き先はチベット。夏休みを利用しての2週間である。今回も旅行中のメモをもとに旅日記を綴ることにする。
今回の参加者は23名。うち女性は9名、年齢は23才から72才まで、京阪神を中心に九州、関東からも参加。ツアー団長は中国のチベット併合時にインドへ亡命し、その数年後来日されたチベット人のT先生。以来30数年間一度もチベットを訪れることかなわなかったが、このたびようやく初めてのお里帰りができることになったのだ。前回の、インド・ネパール・ブータンの旅でご一緒したメンバーのうち,私を含めて5名が参加した。
チベットは平均標高4000メートルの高地であり、まずは高山病の心配があった。思えば13年前富士山に登った折九合目あたりからひどい頭痛に悩まされ3歩進んでは休む胸突き八丁、あれが私の最初の高山病の経験であった。以来高地に弱いという思い込み深く、前回の旅行の際,標高1700メートルのカトマンズ空港での頭痛を高山病だと言い触らして笑われた。
今回は内科医K先生の伝手であらかじめ名古屋大学医学部の低圧室に入室する機会を得た。旅行に出る5日前のことである。8畳ほどの部屋の中で標高5000メートルの状態まで気圧を下げるというのである。このとき5名が一緒に入室したのだが、その中でまっさきに嘔吐したのは私であった。4500メートルを越えた途端のことだった。この後激しい睡魔とむかつき、頭痛は、3000メートル台に降りるまで続いた。以来“魔の4500メートル”が記憶されることになる。
不安はあったが、何とかなるだろうと思う。ただ、低圧室5000メートル地点での頭重感がもし何日も続くとすればいやだなと思った。高山病の予防としては漢方薬の柴苓湯あるいはダイヤモックスといういずれも利尿剤が効くという話であった。要は体の中に浮腫ができるので、それを外に追い出してしまうのがよいということらしい。チベットに着いたらなるべくたくさん水分を摂りなさいよ、とチベット旅行経験者に言われ、薬とお湯を頼りに出掛けることにする。
1991年7月26日 金曜日
7時45分の空港バスに乗り、空港8時40分着。国内線ロビーと国際線ロビーを間違え時間をロスし、集合時間を大幅に越えてコンダクター氏に迷惑をかける。今回はどうも準備段階からバタバタしてしまった。旅行前の多忙は厳禁と言われていたのに、出発前に仕事をためてしまい睡眠不足のまま旅行になだれこむことになったのだ。10時15分発のキャセイ航空でまずは香港へ。旅の入り口としての香港はあまりに日本に似ていて、個人的な感覚ではまだ旅の助走段階である。ハイ・テンション、早口の日本語を操る現地ガイドの許(きょ)さんにより浅水ビーチを案内されてこの日は暮れる。
1991年7月27日 土曜日
朝6時モーニングコール。眠りの中にドリルをさしこまれる。ここロイヤル・パシフィック・ホテルの朝食はお粥、パン、ワッフルなどが並ぶバイキング形式でなかなかおいしい。ゆっくり食べたかったが、廣州行きの列車は九龍駅8:18発のため、許さんにせきたてられ、駅へ。
湿度たっぷりの風景を見ながら約5時間列車に揺られる。この列車の中では蓋つきコップとジャスミン茶が配られ、女性乗務員が魔法瓶のお湯を配って歩く。愛想は悪い。
中国時間12時40分、廣州着。ここで、2人の現地ガイドに迎えられる。ひとりは胡さんという、成都出身の長身痩躯の青年。このひとが旅行のほとんどを同行してくれることになる“全線随行”のガイドなのである。いまひとりは張さんという小太りの中年男性で、廣州のみのガイドである。どういう仕組みか最後までよくわからなかったけれど、中国国内のガイドはすべて公立の旅行案内組織から送られ、どうやら、全線随行ガイドの他に各地で短期間のガイドもつけなければならないようだ。
張さんの“正しい”日本語の説明は許さんのそれに比べると耳に緩やか。繁華街の中山道、光孝寺、六榕寺、孫文記念館をみてまわる、が、暑い。湿気が多い。夕刻空港へ。ここで張さんと別れる。
飛行機で成都へ飛ぶ。移動が多くて疲れる。
錦江賓館での夕食時、コンダクター氏より良くないニュースが伝えられる。悪天候のため本日のラサ行きの飛行機は欠航。明日の便がもし飛べば、今日のあぶれたお客も乗り込むわけで、予約はとってあるものの、必ず乗れるという保証はないという。早めに空港に行く必要があるとのことで5時起床、5時30分出発となる。チベット入りに必要な十分な休息とは随分矛盾するハードスケジュールである。一筋縄ではいかない旅だという予感がこのころから芽生える。搭乗券を握り締めて大勢の客が我先にと飛行機目指して走るのだろうかなどとぼんやり思いつつ、部屋でなかなか届かない荷物を待つ。
1991年7月28日 日曜日
5時30分出発。まだ暗い中をバスは走る。畑の中の一本道を猛スピードで走る。そのバスの右手を大きな荷物を乗せた自転車が、同じくらい悠々と走っている。成都ではとにかくみんながひた走っている。
早朝のためまだ電気もつかない空港でアナウンンスを待つ。搭乗券はあっても乗れるという確証はない。あまり早く出て来たので、朝食もホテル提供のランチボックス。闇中摸索の味がする。
7時過ぎやっと空が明るくなって空港の外、もやの中に木立が見え出す。雰囲気がいい。ブッシュにも広葉樹にも、どちらにも偏らない緑。しっくいを壁に塗った平屋が点々と続く。
幸い、7時40分と7時50分、2便が飛ぶことになり、ラサまで行けることがわかる。7時50分離陸。
ラサに着いたら猛烈に空気はきれいし、調子に乗ってフワーッとなってしまう。4時間は皮膚呼吸で保っていられるが、その後がくっとくる。支えられてフラフラになって歩いとったフランス人を見たが、あれはかっこわるいなあ
出発前Dr.Kに聞いた話である。着いてすぐは妊娠後期の女性のごとくそろりそろりと歩かねばならないという示唆もあった。しかし飛行機の中にいる限り、まだ想像つかない。
10時ラサ空港着。標高3500メートル。空気が冷たい。空が澄んでいる。空港の周りに雪を戴いた山。空港は、一度も建物の中を通過することなく、門すらもない。チベットが飾らなくてやさしく思えるのに、この空気の中に、この気候の中に、私の体力を奪っていくものが隠れているのだろうか。半信半疑。
バスの準備が整うまで、気功のまねごとなどして待つ。手の平を上に向けて陽の動きにすると、空気が暖かく、逆に手の平を下向けにした陰の形では冷たく感じられる、ような気がする。なんとなく頭がぼーっとして幸福な感じなのは高山病のきざしか。寝転ぶと大地のひんやりした感触が伝わってくる。フロントグラスのひびをテープで補強したバスに乗り込む。チベット人ガイドのロマさんという若い女性が加わる。
チベット第1日の今日はなるべく低い土地で、という配慮から、直接ラサ入城せず、南のツェダンへ。
途中ヨンブ・ラカンを見る。ここはチベットの父祖降臨の地。小高い丘の上に古い寺がある。バスから降りると子どもらが駆けてくる。“こんにちは”は“タシデレ”。ラヒという名の男の子と一緒に寺へ登る。歩きながらチベット単語を教えてもらう。目はミ、鼻はナゴ、口はカー、あごはオマ、耳はアンジュ、頭はゴーで、脚はガンバ。寺の上には塔があり、何十年もの間お経を書き写している老人がいた。塔の上の小窓から東の方向にタルチョンがいくつもしがみつくような感じで揺れている。チベットは犬が多い。あちこちでのっそり寝そべっている。寺の階段もベッドにしていて笑ってしまった。子どもたちと別れ、バスに乗る。
昌珠寺へ。ここには真珠でできた観音像があった。人を助け疲れてしばし休息しているという。左肩にかしいだポーズが優雅。ここにも子どもが群れていて、先程の寺の子よりもactiveに、手をつなぐのを求めてくる。年長の少年がこっち、と指で合図しては“マショー”とか“ヤンソー”とか言う。“行こう”という意味かと思って、私も「マショ、マショ」と言いつつついていく。2才前くらいの男の子も子ども集団に一人前にまじっていて、関西でいうところの“ゴマメ”か。ひとりで行動できるときはひとりで、はしご状の階段では、年長の女の子が手を貸したり、おんぶしたりする。必要なときに面倒をみてやるのが極めて自然である。
ツェダン・ホテル着。食後胃にむかつきを覚え、ダイヤモックス2錠、柴苓湯、セデス服用、大量の水を飲む。20分ほどして痛み和らぐ。明日は、王家の墓を見る予定を変更して、チベット最古の寺,サミエ寺を訪れることになる。
Posted by ボブ・マリ at 13:07│Comments(0)
│旅